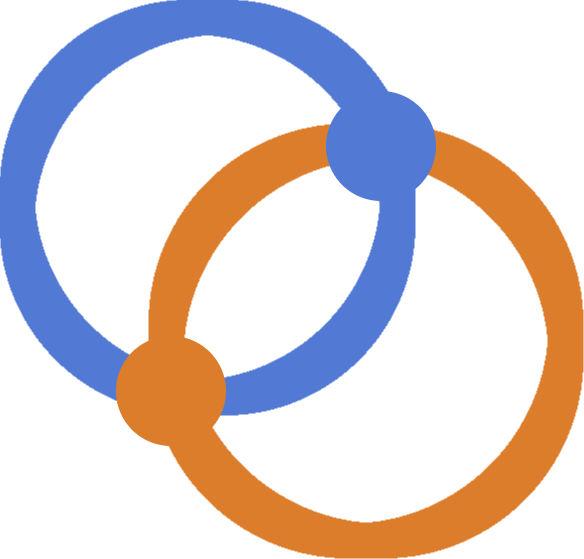前回は民事裁判での事実認定と証拠について説明しました。
民事訴訟における証拠
相談を受けていると、どうしても「あなたの言い分が真実であれば、あなたは裁判で勝てる可能性はありますが、証拠は何かありますか」と尋ねなければいけません。
裁判になった場合には、証拠が無いとその事実が認定されないからです。
相談者の方が「A氏が自分から金を借りたことは、Bも知っている」「Bが証人になってくれる」と言われることがよくあります。
これで証拠として十分か、というと、悩ましいところです。
Bさんは、あなたの味方とは限りません。裁判になると、協力してくれないかもしれません。そうすると、こちらの証拠は何もないことになってしまいます。
また、いざ裁判になると、Bさんが知っている理由は、「お金を渡すところに立ち会った」ということではなく、「(相談者が)Aに金を貸していると、いつも話しをしていた」ということだけかもしれません。そうなると、Bさんが知っている事実は、Aさんが話しをしていた、ということではなく、目撃者でもないことになります。これでは、証拠としては、頼りないということになります。
証拠は書面で
そこで、どうしても、契約書や領収証といった証拠がないか確認することになります。
証拠があれば、苦労しない、ということかもしれませんが、「証拠がない」ということは、それだけで不利な事実となります。
例えば、高額のお金を支払えば、領収証を作成するのが当然です。そうであるにも関わらず、領収証が無いということであれば、不自然だと思われます。
同様に、高額の取引であれば、契約書を作成するでしょうし、お金を貸したのであれば、借用書を作成するでしょう。
このように、通常あるべき書類は無いという事実は、裁判を闘う上では、厳しいものがあります。
この通常あるような証拠が当たり前にある、ということが裁判では重要であり、客観的な物、押印がなされた書面が重要となります。
そして、このような書面等に比べると、人の供述は危ういものがあります。一般論として言えば、証拠の価値としては、書面等の客観的証拠が重要であるということになります。
裁判には証拠が必要だということを意識すると、契約書、領収証は大事なものであって、正確に作成し、きちんと保存しなければいけないと分かると思います。
紛争を予防する上で、証拠は重要です。後々が不安であれば、作成すべき書面等、専門家に相談をされることをお勧めします。
証拠の中でも、証言について説明をしたいと思います。
テレビドラマ等での裁判のシーンは、法廷で尋問をしているシーンばかりです。そこで、裁判の経験が無い方は、裁判ではいつも華やかな尋問が繰り広げられていると思われがちです。
しかしながら、実際には、民事裁判では尋問に至るまでに相当な回数の書面のやりとりがなされており、証人尋問が行われるのは最後の最後となります。尋問までの手続きは、映像的には実に地味です。
証人尋問では、双方の主張の食い違いについて、実際に当事者が質問に答える形式で進められます。
なお、私の感覚では、実際に裁判となった民事訴訟のうち半数以上が尋問の前に和解で終わる例が多いように思われます。この和解手続については、別途、説明をしたいと思います。
民事訴訟の場合には、尋問をする証人は、原告もしくは被告が有利な証言をしてくれると見込んで証人申請をすることが多いです(もちろん、第三者的な証人もいます)。
このような証人の場合、一方に有利な発言をしがちです。どちらかが嘘をついているのか、同じ事実を違うように評価しているのか、その内心は分かりませんが、同じ事実について確認しても、証人によって随分と違う話が出てくるものです。もちろん、嘘をついてはいけません。嘘をつかないように、証人は宣誓もしなければならないのです。
証人尋問では、最初に自分の側の弁護士から質問を受け(これを主尋問といいます)、次に、相手方の弁護士から質問を受けます(これを反対尋問といいます)。主尋問での質問と回答は練習をして来ているわけですから、あまり面白いことはありません。逆に見所となるのは、反対尋問ということになります。意表をついた質問から、証人の矛盾が発覚するなど、様々な展開がありえます。
弁護士としても反対尋問でうまくこちらに有利な証言を得られれば、大きな成果となりますし、気持ちのいいものです。もちろん、これだけで勝訴できるわけではありませんが、有利な事情となることは間違いありません。
こうして、両当事者からの尋問が終わると、裁判所からの尋問があります(これを補充尋問といいます)。補充尋問での質問は、実際に裁判所が判決を書く際に気になる点を聞くので極めて重要ですし、尋問内容についても「なるほど」と思うことが多々あります。
こうして、尋問が終了すると、一通りの手続きは終了したことになり、あとは判決を待つばかりとなるのです。
この後の手続きは、次回の説明とさせてください。
本コラムはリスク法務実務研究会にて当事務所の弁護士小川剛が担当している内容を、一部改訂して掲載しております。
小川・橘法律事務所 無料法律相談のご予約